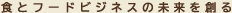お魚模様の番屋へ集結!
私のほうは、その年の8月17日、初めて志津川を訪ねた。
旧知の木更津の漁師、金萬智男さんとその仲間たちが、被災地へ中古船を送る活動をしていた。その途上で、工藤さんたちに出会い、船を届けることで絆が生まれていた。私はフェイスブックでその様子を見るうちに、「この人たちに会いたい」と思うようになっていた。
7月のある日、金萬さんから「工藤ちゃんたちが、東京に来ているよ」と教えられ、私は銀座までのこのこ会いに行った。その飲み会の席で、工藤さんが話してくれた。
「奥田ってシェフが、志津川に来てね……」
「さすが奥田さんですね。今度は私も志津川に行きたい!」
「いいよ、電車の線路が津波でなくなっているから、最寄りの駅まで迎えにいくから」
今考えると、被災者である工藤さんに迎えに来させるなんて、不届き千万もいいところだったのだが、「いいよ」と言われたからには行くしかない。
そうしてたどり着いてびっくり!
何もない港に、ポツンと、お魚模様の建物が建っている。まるで水族館のようだ。

震災直後、工藤さんはじめ20人ほどの漁師仲間は、無事だった船や潜水の機材を使い、海のガレキ撤去作業をしていた。
「今、みなさんに一番必要なものは何ですか?」
そう尋ねたのは、当時工藤さんの次男・茂樹さんが通っていた宮城大学の竹内泰准教授。
「家も作業小屋も流されて、みんなが集まる場所がない。漁師の作業小屋、番屋がほしい」
それを受け、東北や東京、関西から学生やボランティアが集まった。総勢62人。彼らの協力と支援で、震災から2カ月たらずの5月7日、番屋が完成した。
7月にやってきたのは、仙台にある東北生活文化大学の学生たち。その生活美術学科には、絵の得意な子が多い。
学生「私たちにできることはないですか?」
工藤「番屋の壁に絵を描いてほしい。何でもいい。みんなの気持ちが明るくなるように」
学生「わかりましたー!」
というわけで、学生たちが熱中症も顧みず、炎天下で描いたのがこの図柄。周りの建物はなくなっていたので、このカラフルな番屋は、遠くからでもよく目立つ。
こうして彼らは「志津川の番屋チーム」と呼ばれるようになった。
当時のメンバーは15人。牡蠣、ホタテ、ワカメ、ギンザケ、ホヤ……志津川湾で育つあらゆる海産物を養殖している漁師が勢ぞろい。みな30〜40代の働き盛りで、工藤さんのように20代の息子もまた漁師という人もいる。また、漁協の青年部長の経験者が7人もいる、精鋭チームでもある。
話を戻そう。私が訪れた日は、朝からみんなで釣りに出ていたという。
「どれどれ、何が釣れたんですか?」と見せてもらうと……

それは、丸々と太ったギンザケだった。
ギンザケは、海に浮かべた大きないけすで育てる養殖のサケ。一般的に「サケ」と呼ばれるシロザケは、稚魚を放流して戻ってくるまでに4〜5年かかるが、ギンザケは稚魚をいけすで育てれば、半年もすると3〜4㎏の出荷サイズになる。
そもそも志津川は、日本の「ギンザケ養殖発祥の地」。1975年、全国に先駆けて養殖技術が導入された。一時期湾内のどこもかしこもギンザケのいけすが浮かんでいたが、のちにチリから安価なギンザケが大量に輸入されるようになり、撤退を余儀なくされた人も多い。それでも継続していた養殖いけすは津波で流され、中にいたギンザケは、そこから大脱走していたのだ。

工藤さんの仲間で、ギンザケを養殖していた渡邊剛さん(50歳/写真)も、津波でいけすを流されていた。
「ギンザケはいけすの網の中に入っていたから、津波に揉まれて全部ダメになったと思っていました。ところが震災後すぐ、近くの川へ上ったんですよ。やっぱ習性なんでしょうかね。傷ついて力尽きたギンザケを見て、ああ、もったいねえなあと」
ところが、中には生き延びたギンザケもいた。沿岸の海を北上し、岩手県沿岸の定置網にかかったことは、ニュースにもなった。
「オレにはよそで捕まったサケを、取り戻す権利はないです。しょうがない。でも、生きてたんだなあ」
この日、番屋チームが釣ったのは、逃げずに志津川の海をウロウロしていたギンザケ。製氷工場も加工場もないので、釣ったそばから発泡箱に詰め、知り合いや世話になった人に送っているという。逃げたギンザケへの未練を断ち切った渡邊さん。
「新しいいけすを発注しました。こんな時は値段が上がるんですよ。ひとつ50〜60万円はするかな? 地元の鉄工所だけじゃ間に合わない。うちのいけすは、ハマチの養殖がさかんな北陸から来るらしい。11月にはまた稚魚を入れて養殖を再開します」
海は宝だ!
せっかく来たので、漁船に乗せていただき、真夏の志津川湾を見せてもらうことになった。以前は、養殖いかだがいっぱいで、過密状態だったが、この時はホントに静かで、鏡のようにキラキラ光っていた。彼方にポツポツポツ。黒い浮き球が浮かんでいる。
「あれが、震災後、最初に種牡蠣を仕込んだところだよ」
と教えられた。

牡蠣の養殖は、漁業の中でも農業に似ている。種を仕込んで、土の代わりに海がそれを育てるのだ。宮城の種牡蠣は有名で、日本国内はもちろん、フランスなど海外でも使われている。同じ牡蠣漁師でも、種牡蠣を育てる人と出荷用の牡蠣を育てる漁師は別。宮城県では、石巻の万石浦や東松島など、地形が湖のようになっていて、波がとても穏やかな場所で種牡蠣が作られている。ことに万石浦は津波を避ける地形だったため、からくも種牡蠣が残っていたのだ。
奥田シェフが来て、種牡蠣を投じてから3カ月が過ぎていた。小さかった牡蠣は猛スピードで、ぐんぐん育っているという。
牡蠣は海中の植物プランクトンを捕食して育つ。
「津波で海が撹拌されて、きれいになった。ほかのいかだがない分、競争相手が減ったから、今海にいる牡蠣は食べ放題」なのだという。
震災から5カ月、番屋チームには、家を流されたり、親族を亡くした人もいる。それでもみんな強気で、前しか向いていない。
「オレたちはまだ若いから、今から東京に出て、仕事を探せばメシは食える。だけど、せっかく親からもらった漁業権がある。『海は宝だ!』とずっと思ってる。ここに集まったのは、三陸で一番早く再開しなきゃイヤだと思っているヤツばかり。オレたちの自由にやらせろ! ちゃんと儲けてみせるから」(工藤さん)

番屋の前に、メンバーが勢ぞろいした。震災以来、いろんな人がやってきて、支援してくれた。奥田シェフもその一人。
「津波でなくなったものは仕方ない。これからいかに楽しくやっていくか。今はとにかく支援を受けてチカラにしよう。昔は牡蠣作ってたけど、今は友だち作ってる工藤です!」
と笑い、工藤さんはこう言った。
「こっから、海をリセットだ!」
怒濤の勢いで、志津川の漁師たちの巻き返しが、始まる。
1969年山形県鶴岡市生まれ。2000年「アル・ケッチァーノ」を開業。地元で栽培される食材の持ち味を引き出す独自のスタイルで人気を博す。「食の都庄内」親善大使、スローフード協会国際本部主催「テッラ・マードレ2006」で、世界の料理人1000人に選出される。07年「イル・ケッチァーノ」、09年銀座に「ヤマガタ サンダンデロ」をオープン。東日本大震災の直後から被災地へ赴き、何度も炊き出しを実施。今も継続して支援に取り組む。12年東京スカイツリーにレストラン「ラ・ソラシド」をオープン。スイスダボス会議において「Japan Night 2012」料理監修を務める。「東北から日本を元気に」すべく、奔走中。
http://www.alchecciano.com
1965年宮城県生まれ。食材の世界を中心に、全国を旅するかーちゃんライター。16年前、農家レストランで修業中の奥田氏にばったり邂逅。以来、ことあるごとに食材と人、気候風土の関係性について教示を受ける。震災後は、東北の食材と生産者を訪ね歩いて執筆活動中。「農耕と園藝」(誠文堂新光社)で、被災地農家の奮闘ぶりをルポ。東北の農家や漁師の「いま」を、「ゆたんぽだぬきのブログ」で配信中。
http://mkayanooo.cocolog-nifty.com/blog
![FOODLABO[フード・ラボ]](../../img/interface/logo.png)