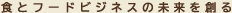絶滅寸前のコケも復活

セリはもともと野草ではあるが、現在は品種改良も行なわれ、苗を作って栽培する。種をまいて育てる種子繁殖ではなく、苗を作って増やす栄養繁殖。白い花が咲いた株を束にすると、そこから新芽が出てくる。それを短くカットした“セリもやし”のような苗を、元肥を入れて代掻きした田んぼへパラパラと撒いていく。
「ちょうど箱育苗が始まる前に行われていた、イネの“水苗代”と、ほぼ同じ方法です」
田んぼに時期をずらしながらパラパラ撒いた苗は、どんどん成長する。すると今度は伸びてきたセリを木の板などで踏みつけて「倒す」。これは三浦さんが大先輩の農家に教わった、名取特有の方法。そうすることによって「もうだめだ、しんどい。それでも繁殖しなくちゃ」と(おそらく)思ったセリは、次の新芽を伸ばす。これを「強制更新」という。
「いじめなければ、どんどん上にニョキニョキと伸びていきます」
あえて過酷な状況に追い込み、ストレスを与えることで、味わいを増す。セリにも試練は必要なのだ。
そんなセリは、セリ田の水位を徐々に上げていくことで茎が太く、長くなっていく。三浦さんは10月〜翌年4月に出荷しているが、管理は1年中必要で、夏の間は、虫や病気がつきやすい。寒くなると風に揺られて枯れてしまったり、鴨に食べられ枯れてしまうこともある。水鳥である鴨の好物は、セリの葉ではなく根っこ。根こそぎセリを掘り起こし、食べてしまうのだ。なのでセリ田の上に防鳥ネットを張り、鳥害を防いでいるが、雪が多いと資材ごと潰れてしまったり、寒さに枯れてしまったり……苦労は尽きない。それでも三浦さんは、農薬や化学肥料を使わずに、セリを作り続ける。
「虫やら、鳥やら、水草やら。一年中水を張って育てていると、いろんな生き物がやってくる。その原理は“ふゆみず田んぼ”(注1)と一緒です。そんな中でおいしいセリを作りたいと、一人でじわじわとやってきました」
三浦さんが、石灰窒素(注2)を使わずに栽培するようになってから、セリ田に「イチョウウキゴケ」が現われた。環境省の「レッドデータブック」で準絶滅危惧種となっている希少な浮遊性のコケ植物で、目を凝らしてよーく見ると、小さなイチョウの葉に似た形をしている。水質汚染や農薬の使用で数が減っていたが、三浦さんの田んぼでは、セリと一緒に水面で揺れている。
- 注1
- 冬の間も田んぼに水を張り、原生動物やイトミミズ、水鳥など、多様な生き物の力を借りて無農薬、無化学肥料で米作りを行なう農法。冬期湛水水田(とうきたんすいすいでん)とも呼ばれる。
- 注2
- 炭化カルシウムと窒素の化合物。窒素とカルシウムを含む肥料であると同時に、土に混和すると、線虫や雑草を防ぐ効果もある。
セリが主役の鍋登場

「農薬や化学肥料を使わない」と、言ったり、書いたりするのはたやすい。しかし、実際は虫との戦いは壮絶。とくに根につく虫やヒルは、出荷時にていねいに水で洗い流しているが、中に紛れてしまうヤツもいる。だからセリを卸す飲食店は、使う前に入念にチェックして、再度水洗いしてくれる……そんな手間をいとわない人たちに限っている。そんな三浦さんだから、いつしか栽培方法の異なる農協せり部会の共販ルートから外れ、独自に売り先を探して販売するようになった。
最初に三浦さんのセリを買い支えてくれたのは、仙台駅近くの割烹料理店「いな穂」の初代親方の稲辺勲さん。2003年、三浦さんの結婚式の二次会の厨房で腕をふるっていたのが出会いで、翌04年、2人で試行錯誤しながら生み出したのが「セリ鍋」だった。鍋に鴨肉のだしを張り、そこへ生のセリをくぐらせて味わう。セリが主役の鍋料理だ。
私に初めてセリ鍋の存在を教えてくれたのは、「伯楽星」で知られる㈱新澤醸造店の新澤巖夫さんだった。「究極の食中酒」を目指した酒造りに取り組む新澤さんもまた、大崎市三本木で140年続いた蔵が大きく倒壊。南へ70キロ離れた川崎町に蔵を移し、再建の真っ最中だった。そんな中、取材に訪ねた私に、仙台駅前の「蔵の庄」という居酒屋で、セリ鍋をご馳走してくれたのである。出てきたのはだしを張った鍋と、鶏肉が少々。そして山盛りのセリだけ。
三好「ホントにセリばっかりなんですね」
新澤「いいから、食べてみて」
復活を目指して新澤さんが醸した「伯楽星」との相性も絶妙で、ひと口、またひと口と食べるうち、ぜんぜん箸が止まらなくなる。
三好「えっ、ずっとセリしか食べてないのに、なんでだろう?」
新澤「三浦さんのセリでなければ、こうはいかないんですよ」
三好「これならどんなに食べても太らないですね。すばらしい!」
と盛り上がったのは、閖上を訪ねた昨年1月のこと。一方の奥田シェフは、今年に入って仙台の知人を介し、三浦さんの「すごいセリ」と、めぐり会ったのだ。
そんなに食べるの、鴨ぐらい


今年2月24日、奥田さんと一緒にあらためて三浦さんの作業場を訪ねると、きれいに水洗いしたセリが並んでいた。これは「名取6号」。セリの味は月々で変わるが、寒さの厳しい2月が最も味がよいという。
奥田さんは、セリを見るなり1本手に取り、シャキシャキと根っこから口に入れリズミカルに食べだした。2本、3本、シャキ、シャキ、シャキ……なかなか止まらない。
奥田「やっぱ違う。丈が短い。色が違う」
シャキ、シャキ、シャキ……まだ止まらない。
三浦「一番おいしいのは、クラウン(王冠)のような形をしている付け根の部分ですね。葉っぱの味、根っこの味、茎の食感が、それぞれ違うので、生でも飽きずに食べられるんです」
奥田「苦みと渋みがクセになる。他のセリは、どうも根っこがゴワゴワしている」
三浦「慣行栽培では、石灰窒素を入れる。それで渋みが強く残るんだと思います」


石灰窒素は、肥料と農薬両方の効果を併せ持つ農業資材。窒素分を補給して、雑草や虫を抑える効果もあるが、三浦さんは鶏糞と油粕主体の有機質肥料を使っている。そんな話をしている間も、シェフの試食は止まらない。その様子を見ていた三浦さんのお母さんが、
「生でそんなに食べるのは、鴨ぐらいかな?」
と半ば呆れ顔で笑っている。するとシェフの背後から忍び寄る小さな影。それは三浦家の庭を散歩している自家用のニワトリだった。地上からセリが乗ってる台を見上げ、チョコッと首を傾げたかと思うと、セリ目がけて飛び乗った。
「コラッ!」
三浦さんの一撃を食らって、しぶしぶ退散。シェフと鴨だけでなく、ニワトリもまたこのセリが大好物のようだ。
1969年山形県鶴岡市生まれ。2000年「アル・ケッチァーノ」を開業。地元で栽培される食材の持ち味を引き出す独自のスタイルで人気を博す。「食の都庄内」親善大使、スローフード協会国際本部主催「テッラ・マードレ2006」で、世界の料理人1000人に選出される。07年「イル・ケッチァーノ」、09年銀座に「ヤマガタ サンダンデロ」をオープン。東日本大震災の直後から被災地へ赴き、何度も炊き出しを実施。今も継続して支援に取り組む。12年東京スカイツリーにレストラン「ラ・ソラシド」をオープン。スイスダボス会議において「Japan Night 2012」料理監修を務める。「東北から日本を元気に」すべく、奔走中。
http://www.alchecciano.com
1965年宮城県生まれ。食材の世界を中心に、全国を旅するかーちゃんライター。16年前、農家レストランで修業中の奥田氏にばったり邂逅。以来、ことあるごとに食材と人、気候風土の関係性について教示を受ける。震災後は、東北の食材と生産者を訪ね歩いて執筆活動中。「農耕と園藝」(誠文堂新光社)で、被災地農家の奮闘ぶりをルポ。東北の農家や漁師の「いま」を、「ゆたんぽだぬきのブログ」で配信中。
http://mkayanooo.cocolog-nifty.com/blog
![FOODLABO[フード・ラボ]](../../img/interface/logo.png)